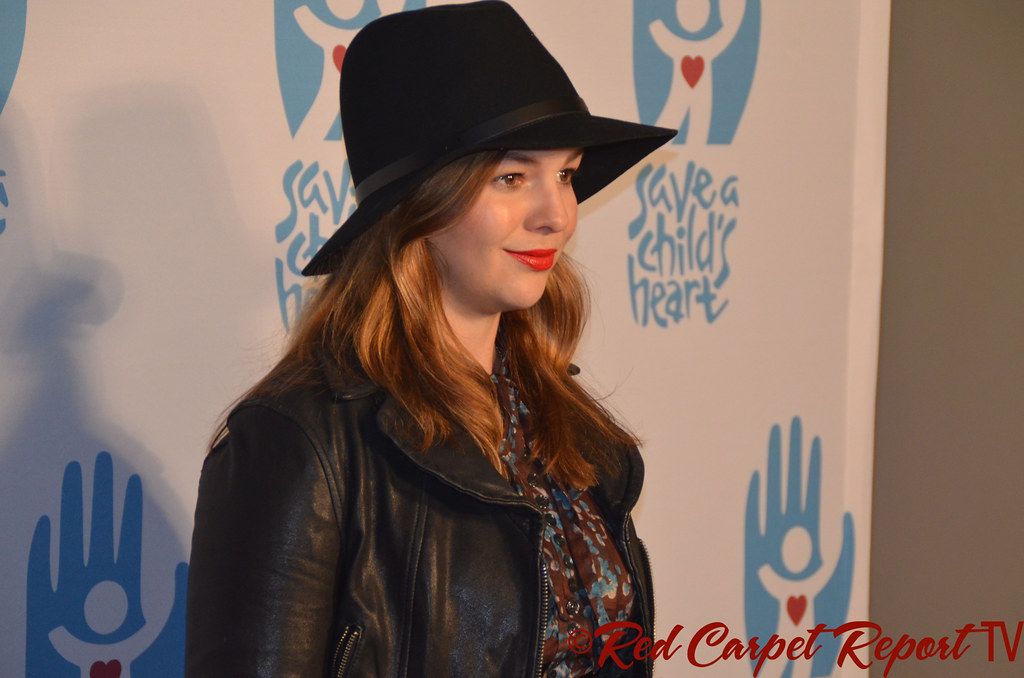『サイド・エフェクト』(2013年)
スティーブン・ソダーバーグの『サイド・エフェクト』を観る。
ルーニー・マーラー演じるエミリーは夫がインサイダー取引によって服役していた最中にうつ病を発症し、夫が出所後もうつが再発したことから、地下駐車場で壁に激突し、自殺を図ろうとしてしまう。そのときにジュード・ロウ演じるジョナサン・バンクス博士がエミリーの担当となり、薬物治療を行っていくのだが、薬の副作用になかなか慣れないエミリーはある薬の広告を見たことで興味を持ち、夫の性生活もうまくいかないことから夢遊病の副作用を受け入れた上で、投薬治療を進めていく。しかし、ある日、彼女は夢遊病の最中に帰宅した夫を刺してしまい、意識がないまま彼女は殺人の被疑者になってしまう。ジョナサン医師は薬の副作用による可能性が高いと述べるが、そのことで自分の築き上げてきたキャリアが同時に崩れて行ってしまう。しかし彼は事実を丹念に追っていくと、エミリーがうつ病を患っていたわけではなく詐病だと築く。以前に彼女の医師だったキャサリン・ゼタ=ジョーンズ演じるヴィクトリア・シーバート博士の論文を見たことで疑念は深まっていき、実は彼女たちがレズビアンの関係で、共謀して犯行を計画していたことが判明する。彼は家族の信頼を失い、同僚からも蔑まれながら、それでも掴んだ真実に基づいて彼女たちの犯行を暴いていく。一度は無罪になったエミリーは同じ罪で二度裁かれないため、精神病棟に治療の必要性があると診断し収監させ、シーバート博士は警察に捕まえさせる。ようやくジョナサンは家族の信頼を取り戻すことができたのだった。
前半部分と後半部分の明確なストーリーの相違が面白く、最後まで飽きないものだった。前半部はエミリーのうつ描写がかなり堪えるもので、観ていると辛さが伝わってくるのだが、後半になるにつれて一体何が真実なのか分からなくなってくる。
ルーニー・マーラーは詐病を演じつつ、目的のために手段を選ばない女性を好演し、キャサリン・ゼタ=ジョーンズは怪しげでセクシーな医師を好演している。とはいえ、ジュード・ロウの実に真っ当な医師っぷりが、キャリアの崩壊に伴って少し偏執狂めいていく過程の描き方はなかなかエグいものがあり、その意味で彼がもっとも好演していただろうとは思うのだった。
『ファニー・オア・ダイ』(2016年)
ジェレミー・コナーの『ファニー・オア・ダイ』を観る。副題は「ドナルド・トランプのアメリカを変えちゃう男 ザ・ムービー」。
ジェレミー・コナー自身が冒頭画面に映り、80年代に作られたある映画のビデオを手に入れたと述べる。それはドナルド・トランプの自伝『アート・オブ・ディール』を忠実に映画化したものであり、この傑作が今初めて人々の目に触れると述べられて、作中作が始まる。かくして映画の中のジョニー・デップ演じるドナルド・トランプは、実にセコい取引の極意を、例によって著しく乏しい語彙で説明し、メキシコ系移民の子役が気に食わなければ変え、日系移民でも気に入らないと結局何度も変えてしまい、皆トランプを翼賛するあまりに馬鹿なことを述べていることにまったく気づいていないまま映画が進む。そして謎のクオリティの主題歌すら流れて終わり、監督自身がそのビデオテープをまったく酷いものだったとゴミ箱に捨てて火をつける。
基本的には『サウスパーク』のノリだと言って構わないだろう。この作品は明確な良心に基づく風刺となっており、その意味である種の力を持ちうるのかもしれない。ただ、この映画が製作された当時と異なる点は、本当にドナルド・トランプがアメリカ合衆国大統領になってしまった、というところであり、この映画の中にある監督で主に体現されてもいる良心というものは、この映画が考えているよりもはるかに力を持たないものであるのかもしれない、ということだろうと思う。
この映画の良心は、前述したように謎のクオリティの主題歌、であろうし、あるいはトランプカードによって挿入される謎の格言シーンの非B級っぽさ、でもあろうし、あるいはわざわざ「モンタージュ」と言われて挿入されるモンタージュ(これは明らかに『サウスパーク』のパロディだということだけは分かった)でもあろう。
ジョニー・デップはかなりいい演技をしているし、この風刺っぷり自体も悪くはないが、現実はすでにその向こう側に行ってしまっている。
『ガールフレンドデイ』(2017年)
マイケル・ポール・スティーブンソンの『ガールフレンドデイ』を観る。Netflixで視聴可能。
ボブ・オデンカーク演じるレイはグリーティングカードなどの洒落たメッセージを書くライターだったが、ここ数年はパッとせず、そのためにクビを宣告されてしまう。しかし、州内で新たに祝日「ガールフレンドデイ」を定めることとなり、そのことがきっかけでカード用のメッセージを書くように元上司から依頼される。だがカード業界を二分するがごとき、兄弟のそれぞれの会社の対立に彼は巻き込まれていき、暴力的な目にも遭う。レイは妻と別れており、そのことが大いに関係してカードが書けないでいるのだが、アンバー・タンブリン演じるジルと出会い、彼女に惹かれていくことで少しずつ立ち直っていくのであった。
例によって『ブレイキング・バッド』や『ベター・コール・ソウル』でソウルを演じたボブ・オデンカークが熱演をしている映画で、正直なところ、悪くない出来だった。微妙にカード業界の対立が分かりづらかったところもあるのだが、人間関係すらも複雑で、別れた妻には同じ業界人の夫がおり、かつて飼っていた猫を共有しているために会いに行かなければならない。ジルについても、薬物中毒の夫との間に子供がおり、しかしそれは父親の養子に入っており、娘は母親を伯母だと思い込んでいる。たぶんこの辺りの設定は、設定上の混乱というよりも、アメリカにおける家族上の前提の一つとでもいっていい有様なのではなかろうか、と個人的には思うのであり、そのために上映時間の短さの割に、こういう要素を詰め込むという選択肢を選んだのだと思われる。
とはいえ、この映画で何が一番よかったかと問われれば、一も二もなく、ジルを演じたアンバー・タンブリンであり、それはまるで『アメイジング・スパイダーマン』で唯一輝きを持っていたエマ・ストーンに匹敵するミューズっぷりを発揮していた。
このアンバー・タンブリンの美しさとは、他者を圧倒するものではなく、私個人を圧倒するものであるのだけれども、ネットで調べてみると詩人ですらあるということで、ミューズだと直感した私の第六感は冴えに冴えている。まさかこういう女優が画面の中に活き活きと映し出されるなど思ってもみなかったわけであり、この新鮮な驚きはボブ・オデンカークの熱演を曇らせてしまうほどのものであった。
残念なことに映っている時間や、その美しさを堪能する時間は短かったのではあるが、その美しさたるや、初めて目にするにもかかわらず、胸が高鳴るのであった。