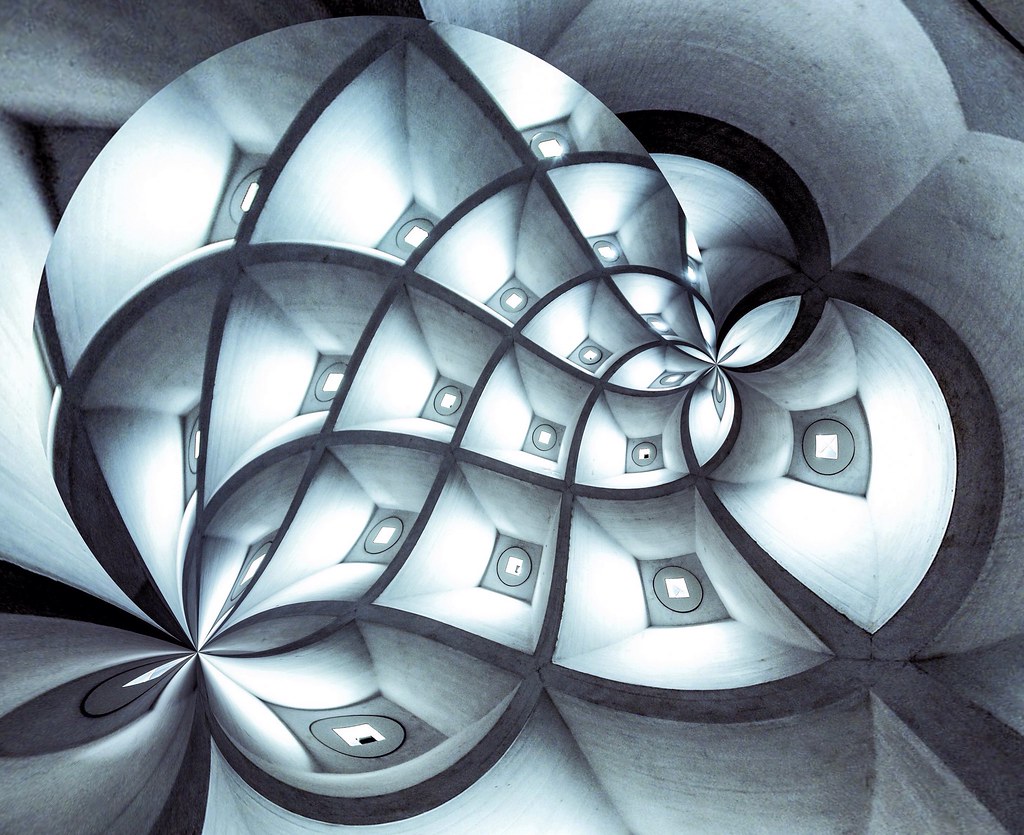迷宮のクオーターライフ・クライシス
思い返せば2016年は呪われていたとしか思えない。2015年の12月くらいから精神的に苦しくなってきたというところはあるのだが、それが改善されないまま2016年に突入してしまった。当時の私は仕事上の環境が大きく変わったことで、もはやどうしようもならない袋小路に入り込んでしまったような気がした。
かくして2016年の後半から休職することに決めた。
2016年度のこの時期は、まったく希望していない出向という憂き目から始まった。とはいえ、最初から悲観的だったわけではない。それなりに頑張っていたし、それなりにコミュニケーションも取り、それなりにマウンティングにも「えへへ」と媚びへつらい、それなりに仕事がうまくできなくて悔しかった。いろいろと仕事の方法を変えようと努力した。嫌いだった自己啓発系の本も読んでみた。あるいは先輩や上司、同僚にアドバイスも求めた。けれども、どうにもこうにもならない迷宮の中にいるようだった。
壁というものは見えるようで見えない。
新入社員で某所に配属され、そのまま初めての異動を経験したときに出向となったのだが、企業文化が異なると、こうも価値観が違うのかと驚いたのを覚えている。それがプラスに転じるものならまだしも、マイナス方面に異なっているのだから、仕事をすればするほど悲観的になっていく。パワハラやセクハラは半ば公然と存在していた。社内政治が横行し、平気で人を駒のように扱った。正直、異動当日に目の当たりにした光景についての印象を忘れることはできない――「ここは軍隊だ」と。
私は生来、のらくらとやる気のない社員として、できるだけ定時で帰って酒を呷りたいタイプであるけれども、早く帰るために仕事を可能な限り効率化し、それを部署全体に広げていくというタイプだった。私が早く帰る以上、同僚も早く帰って然るべきだと、私は当然に思っていた。
出向先は違った。できるだけ足を引っ張る会社だった。そして情報伝達が不合理極まりなく、常に情報が変化し続けた。伝言ゲームの成れの果て、忖度しすぎることの弊害。部署間の争いは熾烈を極め、話しかけようものならば怒声が飛び交う――一体この人たちは何のために働いているのだろう。自分の安定のために他人を不安定にするという信条を胸に、自分の居場所を守るために平気で他人を売った。見て見ぬふりこそが、その職場においては金科玉条であったのだ――もちろんそれが当然であるという職場もあるのだろう。私はそうは思いたくはないのが。
全人格労働という言葉がある。これは仕事に対して、人間存在のすべてをコミットするという思想なのだが、ブラック度が高まれば高まるほどその傾向が強くなるという印象がある。別に仕事なんてできなくても人間としては問題ない。けれども、そうは思えなくなってくるというところにこの全人格労働の恐ろしさはある。目に見えるもの、目に見えないもの、多々あったのだけれども、さまざまな否定を経ていくうちに私は嫌気が差してきた。どうしてこいつらのために俺は働かなければならないのだ、と。
けれども私はいかにも小市民であった。逃げるは恥、と当時は思っていた。馬鹿みたいだが、その後の「だが役に立つ」という言葉を知らなかった。その後のキャリアが完全に閉ざされてしまうということも怖かった。早く家に帰って妻の胸に飛び込みたいと願いながら、同時に仕事上でなるべく成功したいという思いがあった。けれども、働けば働くほど妻との時間は減っていく一方だった。そして互いに不満が募り、そのために喧嘩が絶えなかった。職場でも家庭でも、気の休まる場所がなかった。
結果的には使い物にならなくなった。ほとんどの職務上の命令を遂行することができなくなった。そして上記に戻る。
休職中は好き勝手に暮らした。とはいえ、妻は働いているので主夫として。しかしながら家事労働はいかにも楽しく、それなりにやりがいがあり、それなりに手の抜きがいがあった。本を読み、映画を観た。どちらも弱っていく過程で楽しめなくなっていったものだった。小説も書き始めた。貯金を崩して好きなものを買いまくった(主にパソコンとスマホ、というのが悲しい)。卒業した大学の図書館に歩いて通い、好きなだけ研究書や普段は買えない高い本を捲った。
出向先の上司が同じく病に倒れた。私より酷い状態らしかった。その上司には気の毒だが、当たり前だろうと思われた。元々所属していた会社からは、上司や入社以来お世話になりっぱなしの先輩が、私の復帰のために忙しい中で時間を割いてくれた。申し訳ない気持ちで一杯だった――私は元いた会社に恨みはなかったのだ。とはいえ、復職しようにも出向先に戻る以外に道がなく、私は戦略的に――というと狡く聞こえる向きもあるのだが、果たして体面は健康に対して優位なのだろうか――来年度から復帰することを決めた。
年が変わると、ほとんど私は健康になったように感じられた。私は退屈を覚えるようになっていった。具体的には今すぐ仕事をしたいように思われた。けれども同時に劣等感も培われていった。引け目を感じないわけがなく、いかに出向先の環境が悪かろうと、中途に終わった仕事をカバーする同僚に対して申し訳なさを感じないはずがない。とはいえ、ある一人の同僚は優しく声をかけてくれた。何度か飲みに誘ってくれ、そのたびにフェアな態度で接してくれた。この同僚は同い年ながら、非常に立派な人物である。
私は順調に復職できた――自分でも驚くくらいに希望がほぼすべて通った上で。一説には嫌な上司に当たると、復職が握り潰される恐れがあると言われていただけに、無事に復職できたのは諸々の根回しのお陰なのかもしれない。
復職した今になって思うと、これはクオーターライフ・クライシスという奴なのだろうと思う。実際問題として、人生のある時期に、少なくとも私にとって必要な時間がそれだった、ということである。そして今回のクライシスから導き出される教訓もあった。経験として。
- 逃げ場を作る(人脈、趣味、副業等)
- 楽しい仕事をする
- 無駄な努力はしない(先が見える忍耐は別として)
最後に重要なものとして、「絶対的な正しさ」を私は思う。真っ当さと言い換えてもいい。たとえ百万人が自分に対して間違っていると言っても、神が正しいと言う以上は自分は正しいのだ、といったものである。もちろんこれは簡易にカルトに結びつきかねないものだろうが、間違えてはならないのは、あくまでそれは「よく読む」ということなのだ。
どう読んだって、このように書いているのだから、こうとしか解釈できない、けれども多くの人々はそれを違うという、しかしこのテクストはこうとしか読めない、書いていない、だとしたら、正しいのはどちらか、そのときに一体何が自分の正しさを担保するのか。私はこの時期神によく祈った。今でも、隠れたところにおいでになる父に向けて祈っている。
とりとめもない繰り言ではあるのだけれども、過ち続ける人間に幸あれ。
【参考記事】
表題および記事中の「クオーターライフ・クライシス」という言葉については下記の記事を参照した。
【注記:2018年2月12日、記事末尾の注意書きが不要だったため、削除。】
『バイオハザード:ザ・ファイナル』(2016年)
ポール・W・S・アンダーソンの『バイオハザード:ザ・ファイナル』を観る。
一体どの層がこの続編を、そして最終作を期待していたのだろうか。それは私のような、どうしようもないゾンビ好きである。あるいは第一作を何となく視聴し、アリス演じるミラ・ジョヴォヴィッチの麗しさにやられてしまった以上はある種の義務として最後まで観通さなければならないのではないかという紳士淑女の嗜み、もとい惰性――物理学的に言えば慣性の法則――に則った、偉大なる、ながら観としての映画視聴層こそが、この映画を期待していたのだと言ってもいいのかもしれない。そして監督はと言えば、原作のB級テイストを、まさか予算面ではなくクオリティ方面で発揮するとは、と誰しもが驚き呆れ、なおかつあの麗しきミラとも結婚までしたポール・W・S・アンダーソンであり、それはもはやマイケル・ベイ『トランスフォーマー』(2007年)の主人公よりもだらしない。しかし、前作から、またしても何やかんやあって(としか言いようのない唐突さ!)、結局はレッドクイーンなるAIの導きに従って、第一作、第二作の舞台であり、アメリカ政府の核攻撃によって消失したかと思われたラクーンシティに赴くことになる。第三作で敵役としてやられたイアン・グレン演じるサミュエル・アイザックス博士が再登場し(また再登場かよ!こんなのってありかよ!)、前作で味方になったかと思われたジェイソン・オマラ演じるウェスカーはやはり寝返り、いやもうアリスが捕まったり、アリ・ラーター演じるクレア・レッドフィールドと再会して、彼女の恋人がスパイだったり、てんやわんやで、第一作で唯一の見所である(そして監督もそれを自覚している)狭い通路でのレーザービーム地獄が再現される。かくして、Tウイルスを死滅させる抗ウイルス剤を手に入れるために悪戦苦闘するのだが、アンブレラ社の創業者の娘がアリスの元ネタだったり、レッドクイーンもその娘のデータを抽出したものだったりと、どうでもいい設定が開陳されて、死闘の末にそれを獲得するのだが、好都合なことに体内のTウイルスだけを死滅させるためアリスは死なないのだった。これが風に乗って全世界に広がるまで時間がかかるということで、アリスの旅は続く。
根本的に駄作ではあるのだが、しかしこのシリーズを、完全なる破綻を来すことなくここまでやってきたという、ただ映画を撮り続ける前へ進むエネルギーだけは褒められるのではないのか、と思わなくもないのだが、やはり前作からの連続性がおそらく監督自身も「きっと誰も真面目に観ていないし~」というエクスキューズの下、適当に端折って都合のいいラスト展開に至らしめる、というところは冒頭から感心しない。アリスは一体何のために戦っているのか、どうしてあんなに都合良く気絶するのか、なぜ初めて会ったばかりの連中のリーダーにすぐ収まることができるのか、という諸所の問題は何も解決されないまま、人類が相当数減り続けているために、人間は資源といってもよさそうなのに、さっさと殺され続ける人々が気の毒で仕方ない。あとローラは言われているほど端役というわけではなく、しっかり死に様まで描かれているのでかなりいいのではないか。
おそらく誰も途中まできちんと観ていないために、第一作で登場したハイブを軸にして話を進めたのだろうが、これほど感心しない反復は久しぶりに観たのであり、この感心のしなさ、ということを割と真剣に考える必要はあるだろうと思う。おそらくは(ストーリーがすべてではないとは思いつつも)ストーリーについての監督や脚本の舐めきった態度、があるのではないか、とひとまず睨んでいる。
しかしこう腐してきたわけではあるのだが、けれどもある種の敬意はこのシリーズには払う必要があり、先日観た『アサシン クリード』(2017年)のどうしようもない駄作っぷりと比べると、まだ幾分か「バイオハザード」シリーズはマシだったのではないか、と思うのである。何よりもポール・W・S・アンダーソンとミラ・ジョヴォヴィッチは結婚して子供まで儲けたわけで、そういった意味ではある種、壮大なホームムービーを見せられた、と考えても差し支えはあるまい。
【関連記事】
前作の感想。
『モネ・ゲーム』(2012年)
コリン・ファース演じるキュレーターのハリー・ディーンはメディア企業の社長であるアラン・リックマン演じるライオネル・シャバンダーの下で、モネなどの印象派を中心としたコレクションの収拾と管理に携わっていたが、彼の横柄さに業を煮やし、モネの連作『積み藁』の、長らく行方が分からなくなってきていた「夕暮れ」を、知人の退役軍人であるトム・コートネイ演じる少佐に贋作させ、金を騙し取ろうと画策する。日本人コレクターのゴウ・タカガワとの競りに勝ち、もう一つの『積み藁』である「夜明け」を手にしてから、おそらくその収集欲は天井知らずになったであろう、という思いからである。戦中のナチスによる美術品強奪からの一騒動を利用して、信憑性を高める背景を作り出し、現所有者として、プズナウスキー軍曹の子孫でテキサスに住むキャメロン・ディアス演じるPJ・プズナウスキーを選定する。彼女はカウガールで、無教養ではあるが、ひたむきな性格だった。彼女を仲間に入れることになるのだが、ハリーには悪癖があり、物事を良い方向に考えがちであるといったもので、PJを仲間に加えるときもまた良い方に考えすぎた結果、殴られてしまうことになる。無事にロンドンに連れてきたまではよかったのだが、その後もハリーの思惑通りに事は進まず、ライオネルとPJが男女の関係になってしまったり、ホテルで半裸のままうろつく羽目になったり、資金が底を尽きかけたりするのだった。さらにはキュレーターをクビになりかかりもするのだが、その後は何とか商談に持ち込むに至り、最後にモネの「夕暮れ」を鑑定する箇所でキュレーターとしての眼力の鋭さをライオネルに見せつけ、PJとともにその場を後にする。しかしハリーの目論見は別にあり、実は「夕暮れ」の贋作を売りつけようとしていたのではなく、本当は「夜明け」を盗み出し、それをゴウ・タカガワに売りつけるというものが本来の計画だったのであった。
短めの作品で、サクッと視聴することができる、という点がまずこの映画の素晴らしいところではある。その上で、この映画が仮に120分あったとして、好ましいものと印象づけることが果たしてできたのだろうか、と思うのであった。そういった意味で言えば、この映画がどういった理由があったにしてもこのサイズで出てきた、というところは、まず何よりも監督の力量としては適切だった、と思うのだった。
コーエン兄弟が脚本を書いている、というところで興味を持っていたのだが、視聴しながら、PJを演じるキャメロン・ディアスの魅力に虜になっていた。別にキャメロン・ディアスのことを好きだったわけでもないのだが、ここに描かれたひたすらにひたむきな様子というのはなぜか異様に好ましく感じられてしまい、微妙に知性的な空間から反知性主義(祖母の金言)の勝利に終わるかと思いきや、結局知性の世界へと戻っていく様が、どことなく嫌いになれない自分もいた。
しかし、この映画はある意味で言えば冒頭のアニメーションで終わっていたのではないか、と思わなくもない。