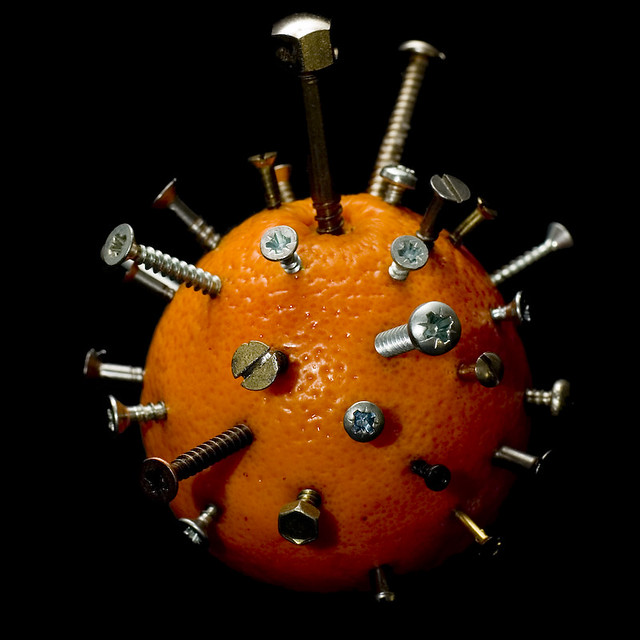『ブレードランナー 2049』(2017年)
![BLADE RUNNER 2049 (SOUNDTRACK) [2CD] BLADE RUNNER 2049 (SOUNDTRACK) [2CD]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/61TrG08BAqL._SL160_.jpg)
BLADE RUNNER 2049 (SOUNDTRACK) [2CD]
- アーティスト: HANS ZIMMER & BENJAMIN WALLFISCH
- 出版社/メーカー: EPIC
- 発売日: 2017/11/17
- メディア: CD
- この商品を含むブログを見る
ドゥニ・ヴィルヌーヴの『ブレードランナー 2049』を観る。
ライアン・ゴズリング演じるKは、ブレードランナーとして旧型のレプリカントを追いかける仕事に従事していたものの、彼もまたレプリカントだった。彼はアナ・デ・アルマス演じるジョイと呼ばれるホログラフィーAIと一緒に恋人として暮らしていたが、あるレプリカントを追いかけている途中で、レプリカントが子供を産んだ可能性にぶち当たる。Kの上司に当たるロビン・ライト演じるジョシ警部補は、秩序を壊しかねないレプリカントの産んだ子供を排除しようと画策するが、前作にてレプリカントを製造していたタイレル社の資産を引き継ぎ、食糧危機を遺伝子工学を応用した合成食糧によって乗り切ることに成功した新興企業ウォレス社に、動きを感づかれる。ジャレッド・レト演じるウォレスは、自らの天才をもっても達成し得ないレプリカントによる生命誕生の秘密に迫るため、自身の側近であるレプリカント、シルヴィア・フークス演じるラヴに、Kを追跡させる。Kはそれとは知らずに、ハリソン・フォード演じるデッカードを追跡する過程で、彼がレイチェルというレプリカントと恋愛関係にあり、レイチェルが子供を産んだということを知る。そして、自身に埋め込まれた記憶を辿っていくうちに、レプリカントに記憶を付与する役割を担っている、カーラ・ジュリ演じるアナ・ステリン博士にKの記憶を聞いたところ、自身の木馬を巡る記憶は疑似記憶ではなく、実際の記憶ということが判明する。彼は自分こそが彼らの子供なのではないかと確信を持つに至って、ジョイはKを製造番号を元にした「K」ではなく、「ジョー」と呼ぶようになる。しかし、その心理的な状況がレプリカントの精神状態のテストに引っかかり、彼はブレードランナーの役割から外れてしまうが、デッカードを追ってラスベガスに赴いたところ、彼と邂逅する。しかしラヴがそこを急襲し、デッカードを拉致してしまい、またジョイを格納したデバイスを破壊されてしまう。Kは、しかし旧型レプリカントを中心とした集団に助けられ、そこで自分がデッカードとレイチェルの子供だと思っていたことは誤りであり、子供は女性なのだと告げられる。しかし、Kに宿った思いは消えず、デッカードを助けるためラヴに攻撃を仕掛け、何とかデッカードを救出することができる。そして、アナ・ステリン博士こそが彼らの子供だという確信を持ったKは、重傷を負いながらデッカードを亡き者として偽装し、彼女の元にデッカードを連れていくのだった。そして、雪が舞う中、ひっそりとKは息絶えるのだった。
とにかく長いのだった。そしてひたすら重低音が鳴り響く劇場の中、この圧迫感を与える音は一体いつまで続くのだろうという感を抱くに至るまで、そう長くはかからなかった。もちろん美術は美しいとは思うし、延々と風景を見下ろす形でしかアングルを指定しない撮影方針は、「地球」という惑星外に宇宙など存在しないかのような、そういう停滞感や圧迫感、閉塞感を感じさせる。その中でレプリカントという、作中であからさまに明示される差別待遇のキャラクターを巡るストーリーを構築することによって、そのあからさまな劇伴が異様なまでの圧迫感を持つに至るのだった。
そして、その長さ、なのである。
ラスベガスに至り、ハリソン・フォードが登場するまでの間、私は何度「早く出てこないかなあ」と思ったのだろう。はっきり言えばリドリー・スコットの『ブレードランナー』(1982年)に、『エイリアン』(1979年)ほどの思い入れがない以上、この圧迫感を受け続けることを良しとする心性が維持できるのも、せいぜいが2時間が限界なのだった。まだしも2時間、観ようという気力が湧くのであれば、まあ映画を視聴する権利くらいは有しようものであると個人的には思うのだが、しかし2時間経っても、ここなのかと思わなくもない。
つまるところ『ブレードランナー』の面白さというのは、まったき意味において美術、であろうと思うのだが、その続編たるこの映画はその美術、というものは楽しめるには楽しめたのだが、何というのだろうか、やはりもう微妙に私たちが変化してしまっているのだ、と思わなくもない。さまざまな映画が『ブレードランナー』の世界観の影響下にあり、その続きを見せられた以上、どこかこの映画の本来持っている魅力というものが後退してしまった、ような、気がする。これは贅沢すぎるのだろうか。
そうは言ってもライアン・ゴズリングはこの微妙な映画に対して、非常に献身的な貢献をしていたと言えるし、ある意味で言えば、このライアン・ゴズリングの存在があってこそ、この映画が辛うじて成立した、と言っても過言ではない。
だが……しかしながら、私が最も注目すべきだと思うのは、ここでKという微妙で複雑なキャラクターを演じきったライアン・ゴズリングではなく、ハリソン・フォードの肉体だと思うのである。
この映画にはそれなりの登場人物がいるのだが、その中で最も異彩を放っているのがハリソン・フォードだろう。一体何が、と問われればこう答えるしかない――肉体が。
『ブレードランナー』においてデッカードを演じたとき、彼の肉体は年相応の引き締まった、解釈の一つとして「デッカードはレプリカントなのではないか?」というものが成立しうるような肉体を持っていた。これは彼が引き締まった肉体を持ち、そしてその肉体の最前面に出てくる顔もまた、そうであったからだ。しかしながら、本作に登場するハリソン・フォードは、どう見たって『ブレードランナー 2049』の中で登場する人物の、誰を見たとしてもだらしなくて、年老いた顔を持ってはいなかっただろうか。
そこには映画の要請している肉体を、いとも簡単に逸脱してしまっている「だらしなさ」が存在してないだろうか。
この映画を色取る、ハリソン・フォードを除くありとあらゆる登場人物は、この映画の想定する「人物(レプリカントを含む)」を超えない範囲の、つまり収まりのいい肉体と顔とを持ち、そうであるがゆえにこの圧迫感をその通りのものとして甘受できていた。しかし、ハリソン・フォードは違っている。この、ハン・ソロを演じ、インディアナ・ジョーンズを演じてきたかつてのスターは、現在、実に自然に年老いていき、(個人的にはそれが魅力的に映ることもなく)かつての役どころを演じなければならなくなっている。そういった収まりの悪さが、映画が要請するキャラクターを簡単に逸脱させてしまっている。
私は彼を見た瞬間、この映画の嫌な部分をすっぱりと忘れることができた。はっきり言ってライアン・ゴズリングの健闘よりも、このハリソン・フォードの「自然」な肉体の方に好意を持つことができたのである。
ここで私が述べたいのは、単に人工は悪い、自然がいい、ということではない。俳優の肉体、というものについての、何か、なのだ。
頭痛の日
頭痛持ち
頭痛に苦しめられることが多くなった。医学的に因果関係について明瞭ではないと聞いたことがあるものの、私の場合、天気が悪くなると頭が痛くなる。
子供のときから、たしかに頭痛に悩まされていたのだけれども、しかし大人になって、しかもアラサーと呼ばれる年齢帯に近づくにつれ、その頻度は多くなった。幸いにして群発頭痛ではないのが救いではあるのだが(友人にそれを煩っているのがいて、それはもう大層辛そうだった)、それでも頭痛というものは避けがたい宿命のような執拗さでつきまとっては離れない。
ゆえに、頭痛が酷くなると家の中に籠もるようになるのだったが――いや、元より家に籠もりがちの私であるのだから、さほど差異はあるまい。卵が先か、鶏が先か――そういう類の話なのかもしれず、あるいは頭痛があるからこそ今の私があるのだ、という逆説もまた成り立つのかもしれない。
遺伝的性質
考えてみると父親も頭痛に悩まされている人間であった。であった、と過去形で書いたものの、これは現在も続いている症候で、決して根治したものではない。そして記憶の中では父親が頭痛を訴え始めると、私の母親はにわかに嫌な顔をしたように思う。
無論のこと心配する気持ちもあった、と母の名誉のために記さなければならないだろう。しかしながら、根本的に頭痛というものは個人的なものでしかないのだ。だから私が頭痛を覚え始めても、それは他人にとっては「見えないもの」でしかない。
頭が痛いとき、頭の血管がドクドクと脈を打ち、あるいは継続的な圧迫感が続き、不快な思いをしながら、それでも活動を止めるわけにもいかず、致し方なく日常的な動作と精神活動を行わなければならないのだけれども、恐ろしいまでに精彩を欠くこととなる。
不安
延々と頭痛薬をポリポリと貪っていくしか解決方法はないのかもしれないのだが、感覚的には頭痛薬の何らかの成分が脳に沈殿していき、それ自体が頭痛を誘発するような性質を持つようになるのではないか、という不安もあるにはある。
セルフメディケーション税制を充分に活用できるのではないか、というくらいに頭痛薬を購入しているような気もしないでもないのだが、その頭痛薬はというと、これまた私がよく罹る風邪を治すための風邪薬とは併用してはならないらしくて、それはそれで辛い思いをするのだった。
頭痛を取るか、風邪を取るか――といった。
同化と異物
知らなかった歴史
少し思うところがあり、長いスパンを設けてではあるのだが、戦時中の朝鮮半島近辺の歴史を学ぼうかと考えているのだけれども、その手始めに後藤明生の出自(「引揚げ文学」の射程から)について気になった。これについては、現在、東條慎生が季刊『未来』にて「後藤明生の引揚げ(エグザイル)」として連載されているらしいので、この連載が何らかの形で纏まるのを待っている。
以上のような怠惰な読者っぷりなのではあるのだが、とにかくこの「引揚げ文学」という視点は私にはなかったものなので、初めてこの視点に気づいたとき、驚くと同時に自分の、歴史に対する無知を恥じ入った。また、この「引揚げ文学」については、朴裕河の『引揚げ文学論序説』の中で知った。
歴史の中の虐殺
数ヶ月前に、『過去改変』という小説を書いた。初めての長編となった作品だったが、この中で関東大震災を扱った第二章があり、関連する文献を読んでいく中で王希天事件という中国人虐殺事件を知った。この小説自体は「流言蜚語」についての多角的なアプローチを基礎としているところがあるので、震災下の東京において、朝鮮人虐殺を始め、一体何があったのか、ということを描き出そうとしている企図があったものの、その成否についてはここでは脇に置こう。
特に第二章においては、ある銀行員の挿話が個人的には気に入っているし、未だに引っかかりがある。これは鈴木淳の『関東大震災』(講談社学術文庫)に書いてあった話を少しアレンジしたのだが、その銀行員はいたって冷静に震災に対応していたのだが、ある条件下において朝鮮人たちに暴力を振るっている。その心理状況は辿っていくと、ある一定の理解を示すことが人によってはできるかもしれない――つまり、自己防衛本能というものだ(断っておくが、私はこの暴力を非常に厳密な意味において、肯定しているわけではない)。
異常な状況下における人間の変貌というものが、虐殺に繋がりかねないし、いや実際繋がっている以上、一体なぜこの状況が生じてしまったのか、ということについて自分なりに状況を整理した上で、「再現」してみたかった。だからこの挿話を入れたし、ある意味で作品全体がそういうものになっていると言える。
「岩本志願兵」
そういった小説を書いているうちに、私は気づかないままあることを見失っていた。私は無意識のうちに、虐殺された方の、排除された方の無謬性のようなものを前提としていた。しかしながら、その側の心理状態について、きちんとした形で想像できていなかったのだ。せいぜい利己的に味方を裏切るようなレベルでしか想像しておらず、その先にある、もっとグロテスクなものについては、たぶんあえて見ないようにしていた。
それは小説上の結構がそうさせたのかもしれず、だからある意味で「引揚げ文学」という視点が『過去改変』を書き上げた後の私には必要だったのかもしれない。
張赫宙の「岩本志願兵」を読んでいるとき、この初めて読む作者の短い小説を読みながら、私は妙に居心地の悪さを感じていた。そしてそれはあるシーンにおいて頂点に達した。この小説は第二次大戦下における日本に植民地化された朝鮮半島において、内地から志願して兵隊となった「岩本」を巡る一挿話を、その軍事教練を見学に来ていた「私」の視点から描くものである。
私は別に民族的なアイデンティティがどうこうと言い募りたいわけでもないし、さほど「愛国心」めいたものは持っておらず、とりわけ、例えば横光利一が盛んに言い募るような意味合いでの「日本精神」というものの純粋さは奇妙でしかないのだけれども(『紋章』における雁金の「日本精神」を見よ)、しかし往々にして以下に引用する心性に人はもろくも達してしまうものなのである。
「内地から初めて来た人は、内鮮が同根同祖だというが、あんなに違うではないか、と、よく申します。そんな人たちには、是非当訓練所へ来るように勧めます。実物を見て成程と感心します。市井の民衆は白い衣服を着、異った家に住んでいて、顔が違う。ですが、それは永い間大陸に依存していた歴史のために歪められたからであって、子細に観察すると、やはり大和民族と同じであることがわかります。今日の朝鮮的なものから大陸的なものを除くと、純粋朝鮮的なものが残りますが、これは純日本的なものに通じるんですよ。百済や高句麗は勿論、新羅でさえ日本的だったんですからね」
「そうしますと皇民化という言葉は、朝鮮の場合には上古還元ということになりますか」
「しかし、単なる還元ではなくて皇民への躍進ですね。同じ根から出た顔が元へ還って、更に同じ皇民精神を把握することによって全く同じものになります。そこで同じ皇国の兵隊になるんですよ」
この話者は日本人ではなく、植民地にされた朝鮮半島の中にいた人々が述べているわけである。
そういえば、先日金井美恵子のトークショーに行ったとき、言い換えは権力側であり、言い間違いは民衆(権力ではない方)の側にあるといったようなことを述べていたのだが、例えば「皇民化」を「上古還元」と言っているのは果たして。